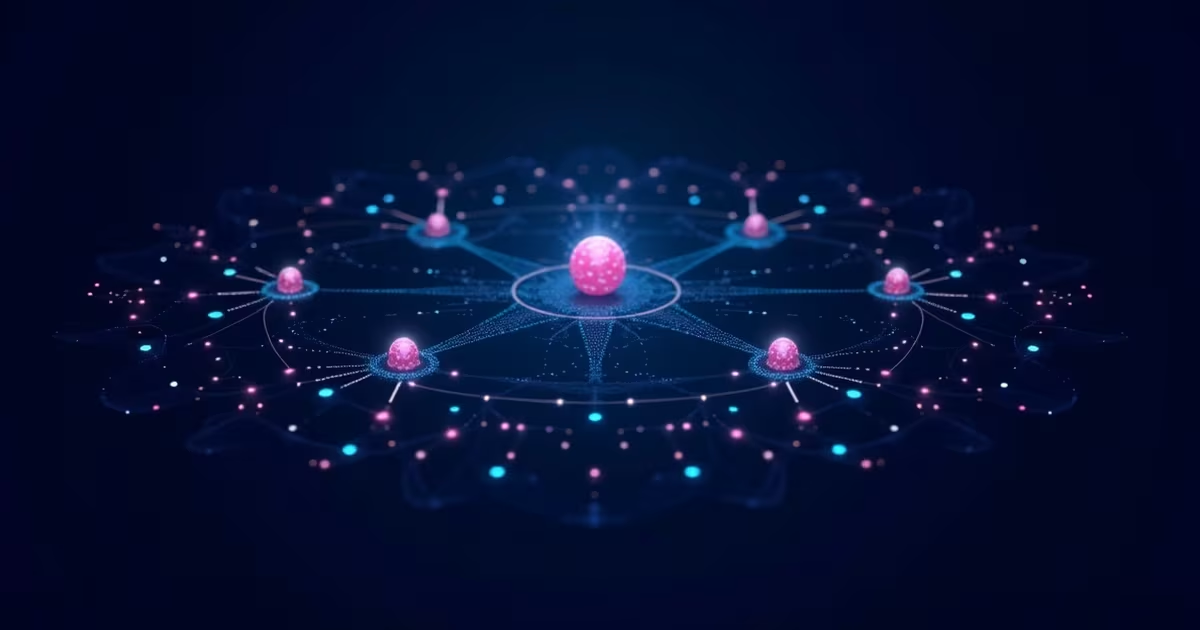DeFiは「オワコン」と言われることがあります。確かに、一度ブームを一巡した成熟したテーマです。
ただし成熟したことと、投資として評価が固まったことは別です。DeFiは、金融という上流のインフラ領域でありながら、トークンの評価軸がいまだ整理されきっていない、少し珍しいテーマでもあります。
取引、融資、清算といった機能はすでに当たり前のように使われています。それにもかかわらず、「使われていること」と「トークン価格で報われること」が一致しない場面が、DeFiでは繰り返し起きてきました。
このズレは、成長テーマのように物語で押し上がる局面では目立ちません。しかし金融という成熟領域では、どこに価値が溜まり、どの立場が調整役を担うのかを見誤ると、判断は簡単に狂います。
この記事は、DeFiの将来性を語るページではありません。評価が固まりきっていない成熟テーマを、感覚ではなく構造で判断するための視点だけを整理します。
DeFiは成熟したテーマだが、価格との関係は一様ではない
同じDeFiという言葉で括られていても、トークン価格との関係や、リスクの出方は分野ごとに異なります。
ここを分けて見ないと、投資判断は噛み合いません。そこで最初に、DeFiを3つに分けます。
DEX:使われていても、価格に直結するとは限らない
DEXは、DeFiの中でも「使われていること」が最も分かりやすい分野です。取引量が増え、手数料が発生している。数字だけを見ると、順調に成長しているように見えます。
投資の視点で見ると重要なのは、その手数料がどこに流れる設計なのかです。使われている事実と、トークン価格が動くかどうかは、ここで分かれます。
ここを押さえずに数字だけを見ると、「一番使われているのに、なぜか価格が伸びない」という違和感を抱くことになります。
つまり、DEXは「使われている」だけでは勝てません。成長がトークンに届く蛇口を握っているか。ここで勝負が決まります。
レンディング:収益があっても、価格とは同義ではない
レンディングは、DeFiの中でも「お金が生まれている」ように見えやすい分野です。金利や手数料が発生しているため、トークン価格にも反映されやすそうに感じます。
ただし、その収益が担保や清算の仕組みを通じて、どの立場に届く設計なのかは別問題です。レンディングの状況と、トークン価格は自動的には結びつきません。
レンディングは収益が出ていても、その利益を受け取る立場にトークンがいるかどうかで評価が分かれます。
同じレンディングでも、価値がどこに溜まり、どこから戻るかは銘柄ごとに違います。その違いは、銘柄分析で確認します。
ステーブル:使われるほど強いが、上がるとは限らない
ステーブルコインは、DeFiの中でも価格の安定を前提に設計された分野です。価値の保存や取引の中継点として使われ、DeFi全体を支える土台の役割を担っています。
投資の視点では、使われていること自体がリターンにつながるとは限りません。安定を目的とする設計は、価格変動を抑える方向に働くからです。
ステーブル関連は、使われているほど“価格が動かない設計”になりやすい。
見るべきなのは、その安定需要が、どのレイヤーで価値の受け皿になっているのかです。トークンを評価するときは、安定の役割と価格の立ち位置を切り分けて考える必要があります。
この3つは、銘柄を見る前に立つ位置を決めるためのもの
ここまで見てきた3つは、DeFiを理解するための分類ではありません。
目的はひとつ。自分が今どの立場で銘柄を見ているのかを判定するための切り分けです。
もし、取引量や利回り、使われているかどうかといった数字だけで判断しようとしているなら、今はまだ見学席にいます。
価値がどこに溜まり、トークンがその蛇口に立っているのかを自分の言葉で説明できて、初めて次の段階に進めます。
DeFiで一番ズレやすいのは、銘柄じゃなく「見ている場所」
DeFiは分野ごとに性質が違いますが、投資判断が崩れるポイントは、実はどの分野でも似ています。
DEXでも、レンディングでも、ステーブルでも、「ここを見落とすと評価がズレやすい」という共通点があります。逆に言えば、この3つだけ意識しておけば、判断が極端にブレることは減ります。
ここでは、DeFiの仕組みを深く理解する代わりに、銘柄を横断して使える、投資家向けのチェックポイントを整理します。
プロジェクトの成長が、トークン価格に反映される設計になっているか
DeFiでは、「使われている」「収益が出ている」といった成長が見えやすい一方で、その成長がそのままトークン価格に反映されるとは限りません。
重要なのは、プロジェクトの成長と、トークン価格が結びつくように設計されているかどうかです。
取引量や利用が増えていても、その価値が別の参加者や別の仕組みに流れる設計であれば、トークン価格には直接影響しないことがあります。
この確認をせずに数字だけを見ると、「使われているのに価格が動かない」「成長しているはずなのに評価されない」といった違和感を抱えやすくなります。
まずは、そのプロジェクトの成長が、トークン価格に反映される前提になっているか。これを最初のチェックとして押さえておくことが重要です。
トークンは、価値を受け取る側か。それとも調整弁か
DeFiのトークンは、すべてが価値を受け取るために存在しているわけではありません。中には、プロジェクトを安定させるための調整弁として使われているトークンもあります。
価値を受け取る側に立つトークンは、プロジェクトが成長したときに、その影響を正面から受けやすい。一方で調整弁としての役割が強いトークンは、需要の変動やリスクを吸収する立場に置かれやすくなります。
この違いを意識せずに見ると、「プロジェクトは伸びているのに、なぜかトークンだけ弱い」という状況に戸惑うことになります。
投資の視点では、そのトークンが成長の果実を受け取る役割なのか、それともシステムを支えるために調整に使われる役割なのかを切り分けて考えることが重要です。
調整弁として設計されたトークンは、プロジェクトが成長しても、価格が報われないまま終わることがある。役割が違うからです。
数字が良いときほど、前提を疑う
DeFiでは、取引量、TVL、金利、発行量など、分かりやすい数字が多く並びます。これらは状況を把握するうえで有用ですが、数字が良い状態=投資判断として安全とは限りません。
多くの場合、数字が最も良く見えるのは、特定の前提がうまく噛み合っている一時的な局面です。その前提が崩れたとき、状況は急に変わります。
特に注意したいのは、「今の数字が、どんな前提の上に成り立っているのか」を確認せずに判断してしまうことです。相場環境、インセンティブ、需要の集中など、前提が変われば、同じ数字でも意味はまったく違ってきます。
投資の視点では、数字そのものよりも、その数字を成立させている前提が何かを一度立ち止まって考える。これが最後のチェックポイントになります。
次は、この3つの視点で銘柄を読む
ここまでのチェックは、「この銘柄を買うか、買わないか」を決めるための結論ではありません。
DeFiは、同じ数字を見ても、見る位置が少しズレるだけで判断が簡単にブレます。だから先に、見る場所を固定するための前提として3つを整理しました。
この前提を頭に入れてから個別銘柄を見ると、何が価格に関係していて、何が深追いしなくていい情報なのかが、切り分けやすくなります。
次の銘柄分析では、この3つの視点を当てはめながら、それぞれのプロジェクトがどんな設計に立っているのかを見ていきます。
資金配分は「金額」ではなく、関わり方で決める
DeFiにどう関わるかは、最初から「いくら入れるか」で決める必要はありません。むしろその考え方が、判断を雑にしやすくします。
ここで考えたいのは、その銘柄と、どの距離感で向き合うかです。同じDeFiでも、学びのために触るのか、テーマとして持つのか、主力として向き合うのかで、取るべき姿勢はまったく変わります。
この章では、資金配分を数字で決める前に使える、関わり方の整理を行います。
テーマ枠:金融インフラとして、役割を決めて持つ
DeFiは、次の主役を当てに行くテーマではありません。一方で、無くなる前提で切り捨てるテーマでもない。
銀行株や証券株と同じように、「相場全体の中で、どんな役割を担っているのか」を意識して持つ対象です。
この枠では、短期の期待や物語ではなく、ポートフォリオ全体の中での位置づけを先に決めます。上がるかどうかよりも、「どんな局面で効いて、どんな局面で効かなくなるか」を理解しておくことが重要です。
コア枠:設計と運用まで理解できたときだけ成立する
DeFiを主力として扱う場合、銀行株で言えば「財務・収益構造・規制リスクまで理解したうえで持つ」のと同じ覚悟が必要になります。
この枠では、使われ方、収益の出方、トークンの役割、そして相場環境が変わったときの弱点まで含めて見ます。
ここまで踏み込めない状態で配分を大きくすると、判断は価格や数字に引きずられやすくなります。コア枠は、銘柄分析と運用ルールがセットになって初めて成立する関わり方です。
見学席:判断軸がないまま入らないための位置
DeFiで一番起きやすい失敗は、理解不足ではなく、判断軸が固まる前に期待で入ってしまうことです。
見学席は、リターンを取りに行くための場所ではありません。どんな情報が効いて、どこから判断がズレ始めるのかを確認するための位置です。
この段階を飛ばすと、配分を増やした瞬間に、判断は数字や物語に引きずられます。見学席は、テーマ枠やコア枠に進む前の安全装置として機能します。
この見方を、次は銘柄分析で使う
ここまでで整理してきたのは、DeFiをどう評価するかではなく、どう見ると判断がブレにくくなるかという前提です。
この前提は、それ自体で結論を出すためのものではありません。個別の銘柄を読むときに、どこを見て、どこを深追いしなくていいのかを整理するための道具です。
次に取り上げる銘柄は、その使い方を確認するための具体例にすぎません。この見方を頭に置いたまま銘柄分析を読むと、同じ情報でも、見え方が変わってくるはずです。
UNI:使われているのに、価格につながらないことはなぜ起きる?
UNIは、DeFiの中でも「使われている」という事実が最も分かりやすい銘柄のひとつです。それにもかかわらず、その成長がトークン価格に素直につながらない場面が繰り返し起きてきました。
ここで確認したいのは、UNIが良いか悪いかではありません。これまで整理してきた視点を使って、どこで価値が生まれ、どこでトークンから離れているのかを見ます。
取引が増えていること、プロダクトが使われていることと、トークンを持つことのリターンは同義ではありません。UNIは、そのズレがどこで生まれるのかを考えるための、分かりやすい例になります。
より具体的な設計や評価については、UNIの銘柄分析で整理しています。
AAVE:利回りが強いほど、環境で顔が変わる
AAVEは、DeFiの中でも収益のイメージが比較的つかみやすい銘柄です。金利という形で価値が見えやすく、好調な局面では数字も分かりやすく伸びます。
ただし、ここで注意したいのは、その強さが常に同じ条件で発揮されるわけではないという点です。相場環境、需要の偏り、清算の起きやすさなどによって、同じ仕組みでも見え方は大きく変わります。
重要なのは、「今の利回りが高いかどうか」ではありません。どんな環境で力を発揮し、どんな局面で弱くなる設計なのか。AAVEは、その切り替わりを意識して見る必要がある例です。
設計や環境依存のポイントを含めた具体的な評価は、AAVEの銘柄分析で整理しています。
SKY:安定のはずなのに、不安になる瞬間はどこから来る?
SKYは、DeFiの中でも「安定」を軸に語られることが多い領域に関わる銘柄です。価格変動を抑える仕組みや、土台となる設計が前提に置かれやすく、感覚的にはリスクが低いように見えます。
ただし、安定は「常に同じ状態が続く」ことを意味しません。設計の前提、担保の質、需要の偏りなどが変わったとき、不安がどこから立ち上がるのかを意識しないと、見え方は急に変わります。
SKYを見るうえで重要なのは、安心感そのものではなく、その安心が何によって支えられているのかです。前提が崩れたときに、どこが最初に揺れるのか。そこを確認する視点が求められます。
安定の土台や、前提が崩れる局面についての具体的な整理は、SKYの銘柄分析でまとめています。